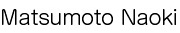expressionの表現という訳語は、あまりうまい訳語とは思えませぬ。expressionという言葉は、元来蜜柑を潰つぶして蜜柑水を作るように、物を圧おし潰つぶして中身を出すという意味の言葉だ。
expressionの表現という訳語は、あまりうまい訳語とは思えませぬ。expressionという言葉は、元来蜜柑を潰つぶして蜜柑水を作るように、物を圧おし潰つぶして中身を出すという意味の言葉だ。— 小林秀雄「表現について」
展示タイトル『魔法使いと魔女』は、ヒップホップの始祖の一人で、その名付け親でもあるアフリカ・バンバータ[1957-]の曲名 “Warlocks and Witches, Computer Chips, Microchips and You” から借用しました。バンバータは、1974年11月、黒人の創造性文化の四大要素〈ラップ、DJ、グラフィティ、そして、ブレイキン(ブレイクダンス)〉を総称して「ヒップホップ」と名付けます(ですから、今月はヒップホップの誕生月なのです!!)。そのバンバータに先立ち、ニューヨーク、ブロンクスのDJであったクール・ハーク[1955-]は、『メリーゴーランド』と呼ばれるを技法を開発しました。それは2枚のレコードを併置し、各々ビートのかかった部分(その多くは曲の「間奏」)—つまり「ノらせる(=人を踊らせる)」部分をカットアップし、つなぎあわせるという方法でした。これが「ブレイクビーツ」の発明となったのです。クール・ハークはダンスブレイクを延長し、ダンサーを踊らせ、MCにラップをする機会を与えた。彼はヒップホップ文化革命の基盤を築いたのである。—— ヒストリー・ディテクティブス(アメリカのテレビ番組)「ノらせる」部分の延長—すなわちヒップホップの誕生は、聴衆の「ブレイキン」をいかに持続させるかという命題によって成立したジャンルともいえます。ヒップホップ[HipHop(=ケツがとび跳ねる)]とは、その名の如く身体を猛り狂わすビーツの「抽出液(オランジュ・プレッセ)」なのでした。リスナーやダンサーたちは、このグルーブに体をまかせ、壊れるほどに身をよじらせるのです。さて、ブレイク[Break]とは、壊す・割る・砕くという意味の他に、前述、ダンスブレイクという語用からもわかるよう「休憩」という意味もあります。曲の間に入る間奏(=Break Beats)では歌はお休みとなります。画家であるアンリ・マティスは「私は人々を癒す肘掛け椅子のような絵を描きたい」といいました。すぐれた肘掛け椅子が身体を「休憩」させるよう、自身の絵画が観るものの疲れを癒すようにと願ったことばです。わたしの作品は、マティスのような巨匠と比較するにはあまりにも拙作ではありますが、それでも会場を提供してくださっているアリコ・ルージュさんのおいしいコーヒーを飲みながら、ゆっくりとご高覧頂ければ幸いです。コーヒーは、もちろん「ブラック」で。
魔法使いと魔女[Solo exhibition statement] | November, 2014

 授業中など、手持ちぶさたにまかせ、シャーペンやボールペンを分解/解 体したり、あるいは幼少のころ、昆虫の脚をもいでみたりと、誰しも、こう した経験があるとおもいます。 きっと元来そのモノに備わっている性質を見定めたい、そうしたムズムズと わきあがる欲求が、無自覚で無慈悲なおこないへと私たちを駆立てるので しょう。なにかの性質を見定めようとしたとき、私たちは、それを限界まで酷使し なければなりません(たとえば分解/解体してしまうほどに)。 それは、なにもモノだけに限らず、たとえば好きな子をわざと怒らせたり、 泣かせたりするのも同じ欲求の表れだといえるでしょう。好きだからこそ、 怒らせ、泣かせるのです(あるいは、あなたは、いじわるをいうと叩かれ、 贈り物をすると涙を見せられるのかもしれません)。陶器は落とすとわれてしまいます。絵の具はベトベトと粘りついてしまう。 押し付ければへこみ、他方ではでっぱる。もしかすると、欠けたり、はみだ したりするのかもしれません。 「無理が通れば道理が引っ込む」とは良くいったもので(無理が通る—— つまりカナヅチで叩いてもわれない陶器は、このときすでに陶器ではない容 器で、物質ではない絵の具は、光か色と呼ばれるものとなるのです)、この「道 理」ということばも、春になれば芽吹き、秋になれば葉は落ちるのと同じよ うに、変えることのできない、こうした欲求と、モノの「質」(の差)にこ そ向けられるべきでしょう。
授業中など、手持ちぶさたにまかせ、シャーペンやボールペンを分解/解 体したり、あるいは幼少のころ、昆虫の脚をもいでみたりと、誰しも、こう した経験があるとおもいます。 きっと元来そのモノに備わっている性質を見定めたい、そうしたムズムズと わきあがる欲求が、無自覚で無慈悲なおこないへと私たちを駆立てるので しょう。なにかの性質を見定めようとしたとき、私たちは、それを限界まで酷使し なければなりません(たとえば分解/解体してしまうほどに)。 それは、なにもモノだけに限らず、たとえば好きな子をわざと怒らせたり、 泣かせたりするのも同じ欲求の表れだといえるでしょう。好きだからこそ、 怒らせ、泣かせるのです(あるいは、あなたは、いじわるをいうと叩かれ、 贈り物をすると涙を見せられるのかもしれません)。陶器は落とすとわれてしまいます。絵の具はベトベトと粘りついてしまう。 押し付ければへこみ、他方ではでっぱる。もしかすると、欠けたり、はみだ したりするのかもしれません。 「無理が通れば道理が引っ込む」とは良くいったもので(無理が通る—— つまりカナヅチで叩いてもわれない陶器は、このときすでに陶器ではない容 器で、物質ではない絵の具は、光か色と呼ばれるものとなるのです)、この「道 理」ということばも、春になれば芽吹き、秋になれば葉は落ちるのと同じよ うに、変えることのできない、こうした欲求と、モノの「質」(の差)にこ そ向けられるべきでしょう。Obuse Alternative 2014[Groupe exhibition statement] | November, 2014.